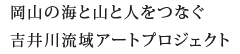川とともに、人とともに。

思い出すたびに、最初にふわりと浮かんでくるのは、家族や友人の顔でも十代の日々でもなく、川の風景だった。
故郷の町を縫うように、流れている幾筋もの川。わたしが子どもだったときには、川辺はかっこうの遊び場だった。当時、小学校にはプールなんてしゃれたものはなかったから、泳ぐのは全て川だったのだ。わたしの夏の思い出は、ほとんどが川にまつわっている。いや、夏だけではない。遠く離れた大都会で故郷を思うとき、よみがえるのも川の匂い、川の音、川の色なのだ。
美作国建国1300年のイベントの一環として、ミステリー小説の執筆を依頼され、身の程知らずに引き受けた。奮闘努力の結果、大傑作が生まれ……と、堂々と言い切る自信はまったくないが、それでも、何とか書きあげて、安堵はしている。
その評価は読者に委ねるしかない(ちょっと、どきどきします)。それはそれとして、この仕事を通して、わたしは改めて川と人との濃厚な結びつきを知ったのだ。かって、美作国と呼ばれたエリアを一週間ほどかけてあちこち回ったのだが、そこには、川と人とがあるときは睦まじく、あるときは戦いの相手として、向かい合い、もつれ合い、結びつき、深く深く関わり合ってきた歴史が確かにあった。高瀬舟での交易ルート、治水工事の対象、水源、遊び場、漁場……そして、文化の発祥地。川は実に様々な顔を持つ。そのあまりの多様さに、目眩む思いがしたほどだ。
その川の一つ、吉井川流域を中心として、アートイベントを繋ぐプロジェクトが計画され、まさに始動しようとしている。
何て、すてきなことだろう。
川で繋がる流域には、言うまでもなく、人々の暮らしと歴史と文化が息づいている。それは、一つ一つが独自性を持ち、それぞれの光を放つ。同じものはないのだ。けれど、その光を繋ぐことで、岡山という場所そのものが大きく見えてくるのではないか。それは、今までとはまったく違う方向から、岡山を照らし出すような気がする。宇野、牛窓、備前、和気、赤磐、美作、津山、奈義。一口に吉井川流域といっても、まるで異なる場所から異なるアートを発信する。全てを均し、平らにし、一つの価値に押し込めるのではなく、各地域、各個人の存在を重んじ、尊び、その意味と意義を認めながら、自分たちの芸術、文化を守り続ける。あるいは、生み出す。あるいは育てようとする。
なんてしなやかで、なんてしたたかな試みだろうか。
まさに川だ。
形に捉われず、変容しながら進んで行く川そのものの発想だ。
硬直した精神からは決して出てこない発想だと思う。
イベントはいつか終わるけれど、このイベントによって蒔かれた種は、そう遠くない将来に必ず芽吹くだろう。
地方の時代と言われて久しい。政治家の口にかかると、どこか虚しくも虚ろにも聞こえてしまう。けれど、こんなイベントを目にし、耳にするたびに、地域から国を、世界を変えていく力が芽吹いていると確かに感じるのだ。そんな力を下支えする仕組みが、岡山にあることを誇りたい。
- PROFILE
- 美作市在住。
- 1991年
- 「ほたる館物語」で作家デビュー。
- 1997年
- 「バッテリー」(角川文庫)で野間児童文芸賞受賞。
- 1999年
- 「バッテリー2」で日本文学者協会賞受賞。
- 2005年
- 「バッテリー」全6巻で小学館児童出版文化賞受賞。
- 2012年
- 日本放送協会放送文化賞受賞。
- 2013年
- 美作国建国1300年記念事業 本格的短編ミステリー推理小説「美作は謎に満ちて」書き下ろし。